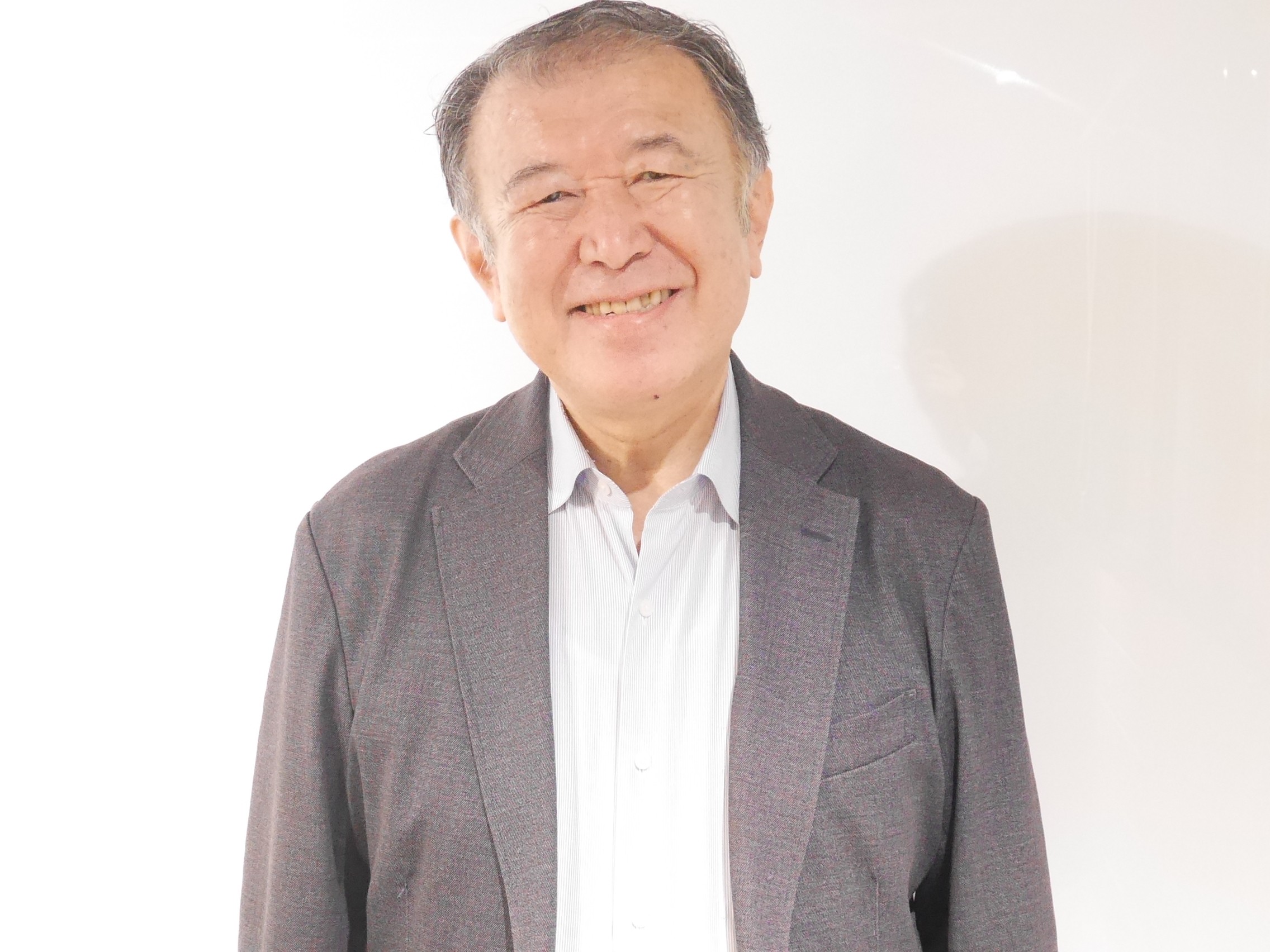EL NEws
アントレ・ラボ通信
今回は、2月13日(金)13時より開催予定の『井戸端会議研修・体験会』 についてご紹介をさせていただければと思います。
人に関わるの仕事をしていると、「対話が大事」「心理的安全性が必要」という言葉を、日々のように耳にします。
けれど実際の現場では、会議では建前の意見しか出てこなかったり、1on1を行っても本音にたどり着けなかったり――そんなもどかしさを感じることも多いのではないでしょうか。
不思議なことに、人は「話し合おう」 と身構えた瞬間よりも、少し肩の力が抜けたときのほうが、自然と本音を語り始めます。
たとえば昔の日本では、囲炉裏を囲みながら交わされる何気ない会話の中に、家族や地域の大切な想いや情報が 流れていました。
評価も正解もない場だからこそ、人は安心して話すことができたのだと思います。
今回開催する「井戸端会議研修・体験会」は、そんな対話の原点に立ち返る試みです。舞台となるのは、趣ある古民家。囲炉裏を囲み、火のゆらぎを感じながら、あえて“研修らしく ない場”で体験を行います。この空間そのものが、心理的安全性を体感するための大切な要素になっています。
この体験会をリードするのが、亀井 凱さんで す。亀井さんは慶應義塾大学医学部に在籍しながら、レモネード合同会社Vice President として事業づくりにも携わる起業家。医師一家 に育ち、「より多くの人生に関わるにはどうすればよいのか」という問いから、医療という枠にとどまらず、人と人との関係性そのものに向き合ってきました。
大学2年次からは、「学生に事業経験を提供し、社会で活躍する大人を育てる」ことをコンセプトに、学生経営BARやインターン採用支援事業を展開。年齢や肩書きを越えた人が安心して集い、語り合える“場”を数多くつくってきた経験は、まさに今回の井戸端会議研修の根幹にあります。現在は、AI時代だからこそ失ってはならない「人間らしさ」や「つながり」 を探究しています。

コラム執筆者
仲津 定宏
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
今年は早い人は27日ぐらいから休みに入っていた人もいるみたいですが、皆様はお休みはしっかり取ることはできましたでしょうか?
弊社の今年のテーマは、『ありのままを伝え、ありのままをカタチ(具現化)にし、ありのままから学ぶ』というスローガン で、「現(表現・具現・現実)」です。
具体的には、3つあります。
1つ目は、「表現:ありのままに伝える」 です。今年は、春までに準備をして、4月以降のアントレ・ラボのYou tubeチャネルなどをはじめたいと思います。
弊社には、ユニークな講師をはじめ、専門家や人財育成に熱心な企業様が多いため、そうした方々をゲストにお招きしの対談などをYou tubeなどで配信する取り組みをはじめたいと思います。
2つ目は、「具現:ありのままをカタチ(具現化)する」です。具体的には、昨年より一部のお客様では先行的に初めている音声ラーニングのサービスを本格的に展開します。音声+αの取り組みで、学びやすさ、継続的に学び、実践する学習を社会に広めていきたいと思い ます。
3つ目は、「現実:ありのままから学ぶ」です。今年は、2月より社員教育に興味のある経営者や役員、人事担当責任者・担当者様の人事に関わる対面での井戸端会議を行っていきます。第1弾は、2月13日に千葉県の佐倉市にある 古民家のいろりを囲みながら、組織における心理的安全性について、お互いの会社での取り組みや課題について、本音トークできる【場】 を作ってゆきたいと思います。
そのアクション内容が、年末における振り返りによる成果に変わってくると思います。
ぜひ年末に良い報告ができるようにしたいと 思います。

コラム執筆者
仲津 定宏
毎年恒例の今年を漢字一文字で表すイベントが京都の清水寺で開催されました。
ニュースでもやっていますが、今年の 漢字は「熊」だそうです。2 位は「米」、3 位は「高」でした。
「熊」が選ばれた理由は、全国で熊の被害が相次いだことや、パンダ(中国 語で熊猫)の中国への返還などが理由に挙げられたそうです。
2位はコメの価格高騰や米国のトランプ大統領就任などから「米」になったそうで、3位の「高」は高市さんの首相就任や物価高などが理由になったそうです。
1位の「熊」と2位の「米」の差はわずか差だったそうです。個人的には「高」がしっくりきますが、皆様はいかがでしょうか?
弊社の今年を漢字一文字であらわすと、「前」だと思います。
理由は3つあります。
1つ目は、今年のテーマとして掲げてきた『一歩前へ』の通り、以前から考えてきたこと、構想していたことが大きく前進したことです。
2つ目は、以前からお付き合い・取引のある企業様との取引の拡大やビジネスの進展が象徴的だったと思っています。
新規を拡大するよりも、既存のお客様とのやりとりに注力させて頂いたように思います。リピートであったり、取引の再開もありました。
3つ目は前向きな1年であったと思います。難があることもまた良いのですが、比較的公私ともに順調に過ごすことができた年であったと思います。毎年のように今年の漢字を考えながら、1年を振り返ることができるのは本当にありがたいことだと思います。先日ある講演で、講師に、そもそも生きていること自体が有り難い。
本当にそうだと思います。

コラム執筆者
仲津 定宏
今日は、2026年1月28日・2月24日より開講予定の『生成AIを活用した採用戦略講座』で講師を務める、株式会社ハイパーメディアマーケティング・代表取締役・菅野弘達様さんにお話をお伺いしましたので、そちらの記事を掲載させて頂きます。
1.現在のお仕事や活動について
はじめまして。株式会社ハイパーメディアマーケティング代表取締役 菅野弘達と申します。1年前までは「ソーシャルメディアマーケティング」という社名でしたが、AIの進化に合わせて変更いたしました。現在はAI、ショート動画、SNSを活用したハイパーメディアによる集客、販促、採用のコンサルティングを行っております。
2.プログラムを開発したきっかけ
少し前まではChatGPTやCopilot、Geminiといった生成AI自体の活用法セミナーが中心でした。しかし現在は「生成AIを使って何かをする」実践フェーズに移行しています。その中で特に需要が多い採用分野に着目し、「AI×採用」プログラムを開発いたしました。
3.プログラムを通じて解決したいこと、目指すこと
現在、日本では業種を問わず採用広告を出しても応募が来ないという課題があります。高額な採用広告費を投じても、条件面で比較されて効果が出ません。AIを活用した広告コピー やSNS投稿、求人文章で他社との差別化を実 現し、応募につながる採用活動を支援しています。
4.今回のプログラムの特徴
AIの使い方に慣れていない方のため、基本的な使い方やプロンプトの書き方から丁寧に解説しています。広告のキャッチコピー、SNSで の投稿テーマなど、具体的な事例を交えながら実践的に学べる構成です。単なる操作説明ではなく、実務で使える内容を重視しています。

コラム執筆者